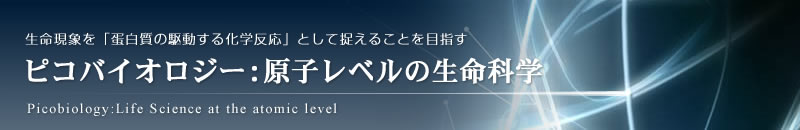|
|
タンパク質は20種のアミノ酸が100個以上つながった鎖状分子である。タンパク質の種類によりそれぞれ異なったアミノ酸配列をもっており、鎖は一定の形に折りたたまれている。タンパク質の機能(生命現象である化学反応を駆動する機能)はこのアミノ酸によって発揮される。 X線結晶構造解析によりこれらアミノ酸の蛋白質中での空間的位置を決定し、それらの機能を、振動分光法によってさらに精密に解析する。その具体的手順は次のように要約できる。 [1] タンパク質を結晶化 [2] X線構造解析によりアミノ酸の空間的位置を決定 [3] 研究対象のアミノ酸だけを標識 [4] 標識化されたアミノ酸の振動スペクトルを測定 これら[1]-[4]の必要性と関連性は以下の通りである。タンパク質を構成するアミノ酸は20種しかないため、巨大なタンパク質は同種のアミノ酸を多数含んでいる。タンパク質は緊密に折りたたまれているため近傍のアミノ酸との相互作用が非常に強く、同一種のアミノ酸でもタンパク質中での近傍のアミノ酸の相違により化学反応性は多様に変化する。そこで、タンパク質の機能解析のためには、まずどのようなアミノ酸がタンパク質中でどのように配置されているか(したがってあるアミノ酸の近傍にはどのようなアミノ酸が配置されているか)を高分解能のX線結晶構造解析法により決定することが必要である。しかし、この構造解析の精度を化学反応の解析の可能な精度(ピコメートル)まで高めることはタンパク質の熱振動のために不可能である。そこで、赤外分光法によって高精度でアミノ酸の構造を解析する必要がある。しかし、同種のアミノ酸が多数含まれているため得られた赤外吸収スペクトルがどのアミノ酸に由来するかを決定することは不可能である。この難点は同位体標識法によって克服することができる。13Cや15N等によって安定同位体標識し、標識された特定のアミノ酸による赤外スペクトルを決定することができる。 |
部門構成
当研究所での研究の特色
| 上述の通り、ピコバイオロジーの目標は生命現象を化学の言葉で記述することである。しかし、既存の化学の言葉だけで記述することは不可能である可能性が高い。タンパク質の機能中心(化学反応の場)は種々のアミノ酸が空間的に配置されて、タンパク質外で人工的に作り出すことが不可能な(極めて困難な)構造を持っていると考えられる。このような構造(化学反応の場)での化学反応はこれまで、化学の分野で取り扱われなかった(知られていなかった)特性を持っていると推定できる。このような化学反応の記述(機構解明)のためには、新規の化学の言葉を作る必要が生ずる。したがってここに(生物学と化学の境界に)新しい研究分野が誕生する。これは生体成分を単なる化学物質の1つとして化学的に(既存の化学の言葉で)構造を研究する従来の「生物化学」とは区別すべきであり、これを「ピコバイオロジー」と呼ぶことを提唱する。 小型の単純なタンパク質系の駆動する化学反応には既存の化学の言葉で十分記述できるものも多いと考えられるが、ピコバイオロジーの構築のためには(新分野開拓のためには)高度に組織化されたタンパク質系の司る生命現象の解明に挑戦しなければならない。そこで、当生命理学研究科で、これまで勢力的に推進されてきた、チトクロム酸化酵素を中心とするミトコンドリア呼吸系の機能研究を当面の課題とする。これら複合体は分子量20〜100万もある巨大な膜タンパク質複合体であり、それらの機能中心はタンパク質の内部に奥深く配置されている。したがって既存の化学の言葉だけでは記述できない「化学反応」が駆動されている可能性の最も高いタンパク質系と言える。また、ミトコンドリア呼吸系は生命の維持のために不可欠なATP合成のための系であり、生命科学の最も重要な研究課題の1つである。したがって世界的な生命科学の研究拠点として当研究所を発展させるための課題として最も相応しいと考えられる。 |