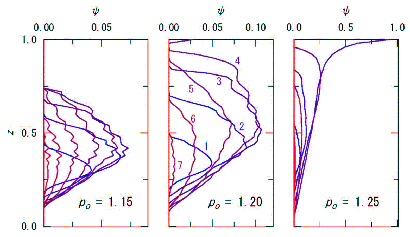井田 喜明 (Yoshiaki IDA)
Updatede 2005.04.11
井田喜明(いだ よしあき)は1941年10月4日東京に生まれる。
1970年3月東京大学理学系研究科地球物理学博士課程を修了し、理学博士の学位を取得。
コロンビア大学ラモント研究所、マサチューセッツ工科大学地球惑星科学科に留学後、
1972年8月より東京大学物性研究所助手、
1977年1月より東京大学海洋研究所助教授、
1986年4月より東京大学地震研究所教授。
2002年4月より現職の兵庫県立大学生命理学研究科(旧姫路工業大学理学研究科)教授で、東京大学名誉教授。
この間、1987年〜2002年に火山学関係の国際誌Journal of Volcanology and Geothermal Researchのエディター、
1991年〜1994年に日本学術会議火山学研究連絡委員会委員長、
1992年〜1994年に日本火山学会会長、
1996年〜2000年に測地学審議会噴火予知特別委員会委員長、
1997年〜2000年に国会等移転審議会専門委員、
1993年〜2003年に火山噴火予知連絡会会長などを勤める。
2003年に交通文化賞受賞。
専門は固体地球物理学。マントルの物性とダイナミクス、地震の震源過程のモデル化、マグマの移動や噴火の発生機構などに関して主に理論的な研究を行ってきた。また、マントル物質の高圧物性、海面変動とマントルのレオロジーの関係、火山性地震・微動の発生機構などに関して、共同で研究を進めてきた。
2002年からは科学研究費補助金・
特定領域研究「火山爆発のダイナミックス」
が始まり、京都大学、東京大学、東北大学、北海道大学の研究者を中心に研究が進められている。井田はその領域代表者である。
このホームページに加えて、各種の随想などを集めた
個人のホームページ
をもつ。また、火山についての一般向けの解説を意図して
火山のページ
をもつ。
TOPへ
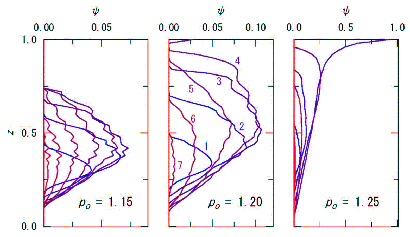
マグマの上昇によって引き起こされる噴火は、爆発性などに多様性が見られる。また、マグマの活動が高まっても噴火に至らない場合もある。マグマの上昇や噴火の性質に関連して、井田は山頂噴火と山腹噴火の関係、マグマの通路としての割れ目の性質、マグマだまりの圧力の蓄積・開放過程、爆発的な噴火を導くマグマの破砕機構などに関して、主に理論的な研究を行ってきた。現在は、噴火の性質や発生条件を明らかにすべく、簡単なモデルを用いて解析を進め、マグマの上昇から噴火に至る過程を、計算機シミュレーションで体系的に再現しようとしている。
図はシミュレーション結果の一例で、マグマ中で気泡の占める体積の比率(ボイド率)ψが、マグマの上昇とともにどう分布を変えるかを示す。zは鉛直上向きの座標で、z=0がマグマだまりの上端、z=1が地表の位置に対応する。ψの分布を示す曲線は時間により色分けされている。マグマだまりの圧力の初期値poが小さいと、上昇を始めたマグマは途中で止まってしまう(左)が、それが大きくなると、マグマは発砲して地表に到達する。その場合、初期値の大きさによって、地表でも発砲度ψが小さく抑えられて、溶岩流として流出する場合(中)と、発砲度が極めて大きくなり、マグマが砕かれて爆発的に噴出する場合(右)がある。
- 井田喜明:マグマの上昇と火山噴火の物理、「マグマのダイナミクスと火山噴火(朝倉書店)」、p67-78, 2003.
- 井田喜明:噴火シミュレータの構築に向けて:重力不安定の成長を基礎に. 科研費特定領域研究報告書「火山爆発のダイナミックス」、vol. 1, p176-179, 2003.
- M. Ichihara, H. Ohkunitani, Y. Ida, and M. Kameda: Dynamics of bubble oscillation and wave propagation in viscoelastic liquids, J. Volcanol. Geotherm. Res., 129, 37-60, 2004.
- 寺田暁彦、井田喜明、大湊隆雄:Windows PCを用いた自動撮影システムによる三宅島火山噴煙の観測、火山、445-459, 2003.
- 井田喜明:非定常なマグマ上昇過程の解析:噴火シミュレータの構築に向けて. 科研費特定領域研究報告書「火山爆発のダイナミックス」、vol. 2, p251-262, 2004.
TOPへ
火山では、火山性地震や火山性微動などの特異な震動現象がしばしば観測される。火山性微動の発生機構を解明するために、様々な形状をもつ振動体の固有振動の理論的な研究を進め、浅間山の事例などに適用した。伊豆大島や三宅島では、火山性微動の発生時に火山全体で微小な傾斜変動が観測され、周期が数秒以上の長い波が広帯域地震計で捉えられた。マグマの活動などとの関連を解明すべく、三宅島などで得られた各種観測データを用いて、震動現象の解析を進めている。
- E. Fujita, and Y. Ida: Geometrical effects and low-attenuation resonance of volcanic fluid inclusions for the source mechanism of long-period earthquakes. J. Geophys. Res., 108B2, 2118, doi:10.1029/2002JB001806, 2003.
- T. Kobayashi, T. Ohminato, and Y.Ida: Earthquake series preceding very long period seismic signals, observed during the 2000 Miyakjima volcanic activity, Geophys. Res. Letters, 30, NO. 8, doi:10.1029/2002GL016631, 2003.
TOPへ
火山噴火予知の実用化や火山災害の軽減に対する社会の期待は大きい。井田は、噴火予知から防災の具体的な方策に至るまで、様々な視点から議論し論評してきた。特に、日本の噴火予知が最近経験した有珠山や三宅島の事例について評価を試み、社会的に大きな影響が予想される富士山の噴火に関して対応策を提案した。また、噴火予知の経験を基に、地震予知の進め方についても意見を述べている。
- 井田喜明:富士山の噴火予知に向けて. 月刊地球、24, 665-671, 2002.
- 井田喜明:ダイヤモンドと噴火予知. 予防時報、No. 213, p6-7, 2003.
- 井田喜明:火山の活動についての予測と情報発信のあり方、火山、48, 141-143, 2003.
- 井田喜明:有珠山と三宅島の噴火、防災情報新聞、92号, 2-3, 2003.
- 井田喜明:活火山の活動度の評価、防災情報新聞、94号, 2-3, 2003.
- 井田喜明:火山災害の要因と対応策、防災情報新聞、96号, 2-3, 2003.
- 井田喜明:火山噴火予知から見た地震予知、月間地球、号外46, 59-67, 2004.
- 井田喜明:地震予知と噴火予知、地震ジャーナル、37, 23-27, 2004.
TOPへ