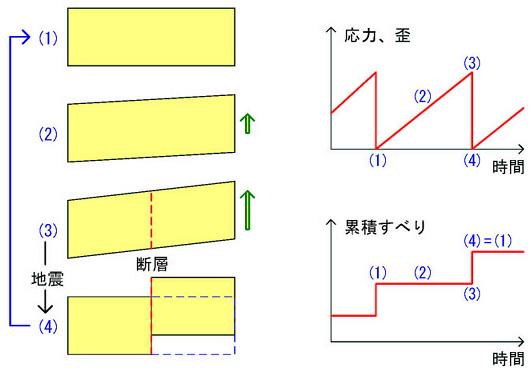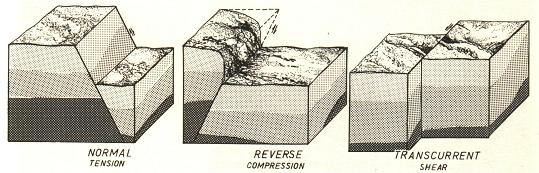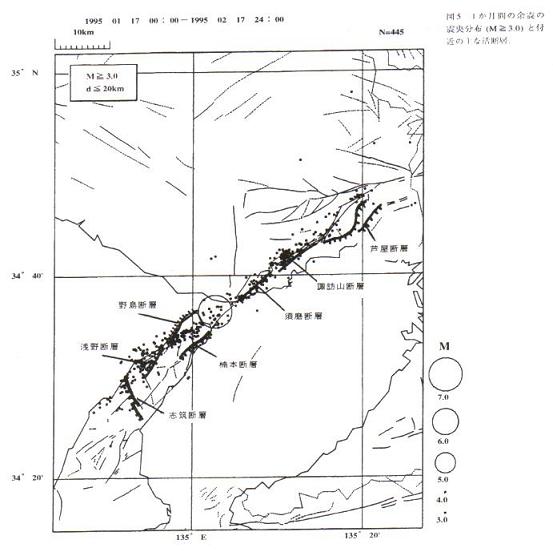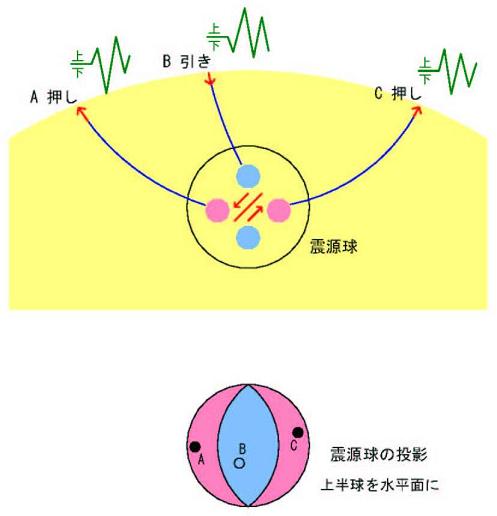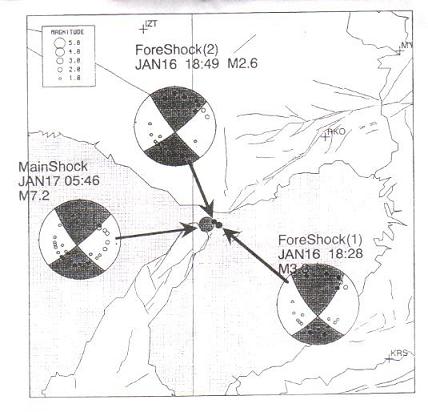4.地震
b. 地震と断層
断層運動(図:弾性反発説)
地震は断層運動によって起こる
断層運動とは、地盤が破壊され、断層面を境にすべりが起こること
蓄積された歪(応力)が断層運動の原因
断層運動の結果として歪は開放
歪の蓄積と開放
地盤にゆっくりと力を加えると、歪と応力は地盤全体で高まる
応力が断層の強度に達したとき、断層面が破壊し、急にすべりが生ずる
断層面でのすべりの結果として、地盤全体の歪が開放される
断層運動の繰り返し
以前すべりを起こした断層は、破壊を受けていない岩石より強度が弱い
応力が再び蓄積したとき、同じ断層でまたすべりが起こる可能性が高い
地震は同じ断層で繰り返し起こる
過去の地震を調べることで、将来の地震の発生場所が予見できる
活動的で、地震を何度も起こす断層を、活断層とよぶ
活断層は、地表で地震の痕跡が見られる断層を指すことが多い
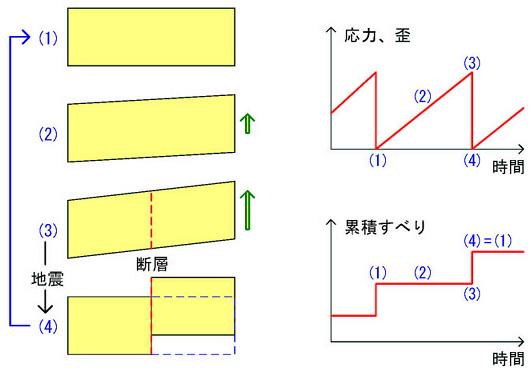
断層のタイプと応力場(図:断層のタイプ)
断層の基本タイプ:横ずれ断層、正断層、逆断層
地盤の受ける応力のタイプを反映。中間的な断層も存在
横ずれ断層:断層面は鉛直で、すべりは水平
断層の向かい側が右にすべる右横ずれと、左にすべる左横ずれ
断層を動かす力は、水平方向のずれ応力(せん断応力)
断層と45°の角度をなす、圧縮力と張力の組み合わせと同等
地震の結果として、ずれ応力(圧縮力と張力の組み合わせ)は開放
正断層:鉛直から傾いた断層面に沿って、片側がすべり落ちる
断層を動かす力は、断層の走行に垂直に働く水平な張力
地震の結果として、張力は開放され、地盤は伸びる
逆断層:鉛直から傾いた断層面に沿って、片側が乗り上げる
断層を動かす力は、断層の走行に垂直に働く水平な圧縮力
地震の結果として、圧縮力は開放され、地盤は縮む
下図:G. A. Eiby "Earthquakes"(Heinemann, New Zealand)より
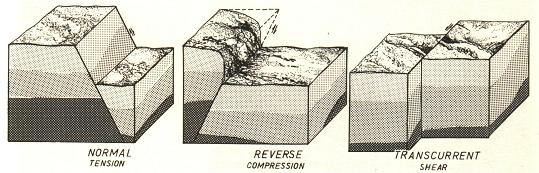
断層の位置やタイプの決定(図:兵庫県南部地震の余震分布と野島断層)
断層運動はしばしば地表で観察される
断層の走行や変位から、断層や応力のタイプを読み取る
本震後に発生した余震の震源分布
余震は、本震の断層付近で起こると解釈
余震の震源分布が、本震で動いた断層の範囲
本震について計算される震源は、断層運動が始まった点
例:兵庫県南部地震(1995年)
本震発生後、淡路島の地表で地割れ
地割れを境に右横ずれ(約1.3m)の変位、南上がりの段差(約0.5m)も
場所は、古くから活動の知られる野島断層の分布範囲
本震の震源は明石海峡の地下
余震の震源は、その北東側と南西側に長さ10〜15kmにわたり分布
余震の分布範囲は、震度7が推定された強い揺れの範囲とほぼ一致
明石海峡の地下で始まった断層運動が、神戸側と淡路島側に拡大
この断層運動は、有馬・高槻・六甲断層帯の活動の一部
神戸側では、地表に断層運動の痕跡は見つかっていない
下図:中田・岡田編「野島断層:写真と解説」(東京大学出版会)より
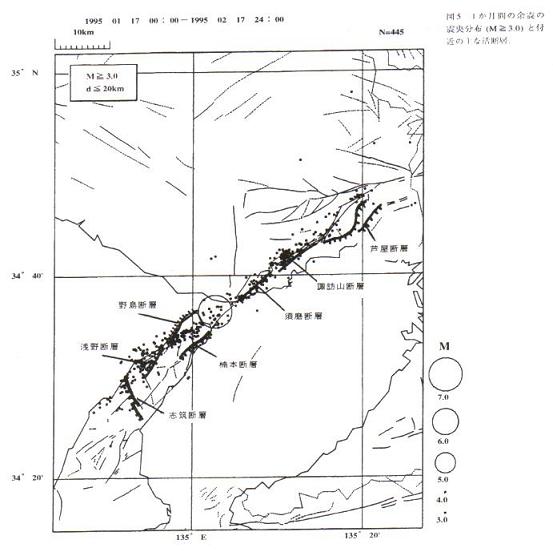
地震のメカニズム解(図:メカニズム解の説明)
断層運動によって、圧縮と膨張の領域が対をなして造られる
断層の周辺で、すべりが向かう方向に圧縮が、遠ざかる方向に膨張が生ずる
膨張と圧縮の領域は空間を4つに分割する;2つの分割面のひとつが断層面
圧縮の領域からは「押し」波が、膨張の領域からは「引き」波が出る
P波初動の上下動成分が、上向きなら「押し」、下向きなら「引き」
震源球とメカニズム解
押し引き分布を表現するために、震源球(震源を囲む小さな球)を考える
観測された押し引きを、波線をたどって震源球上に戻す
震源球上の押し引きを、水平面に投影して表示する
押し引きは、震源球の上半面(または下半面)に集約して投影する
上半面と下半面は、震源球の中心に対して、点対称の関係にある
下半面(または上半面)にある押し引きは、点対称の位置に移してから投影する
断層運動の推定
多数の観測点で押し引き分布から、それらを区画する節面を決める
2つの節面は直行することを考慮する
断層面は節面のどちらか;すべりは引きの領域から押しの領域に
節面のどちらが断層面かは、余震分布などから判断
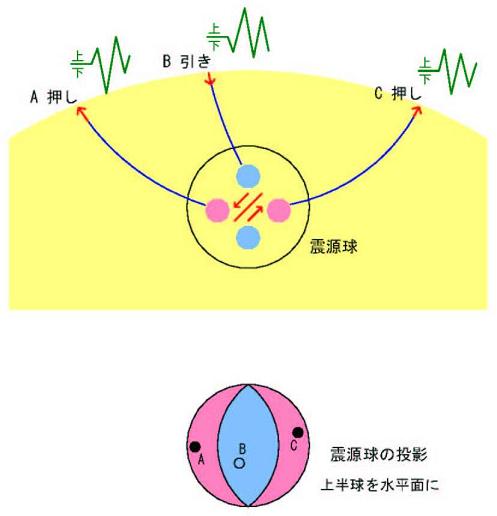
断層のタイプとメカニズム解の関係(図:メカニズム解の典型的な実例)
断層のタイプに対応して、メカニズム解(水平面上の投影図)に特徴
横ずれ断層型:押し引きが直行する2直線で分割される
正断層型:引きの領域を挟んで、両側に押しの領域
逆断層型:押しの領域を挟んで、両側に引きの領域
兵庫県南部地震(1995)(図:兵庫県南部地震のメカニズム解;本震と前震)
横ずれ断層型;断層の走行は北東から南西、右横ずれ
東西方向の圧縮力と南北方向の張力が、断層運動の原因
本震の半日程前に、同じ場所で同じメカニズムの前震が起きていた
新潟中越地震(2004)(図:新潟中越地震の震源分布とメカニズム解)
逆断層型;断層の走行は北東から南西
北西から南東に圧縮力が働いたことが、断層運動の原因
余震の分布には、本震の断層の他にも複数の断層が見られる
下図:深尾・石橋編「阪神・淡路大震災と地震の予測」(岩波書店)より
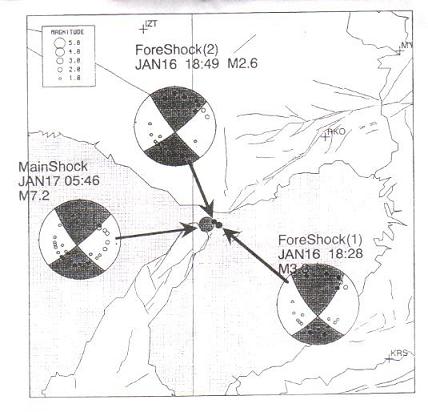
地震の規模のスケーリング
地震の規模と断層の大きさには、経験的な関係がある
断層の大きさとすべり量
断層面積S: log S = 1.0M + 定数
断層の大きさ(長さと幅の平均)L (S = L2): log L = 0.5M + 定数
断層のすべり量u: log u = 0.5M + 定数
地震の大きさは、断層とすべりの大きさを反映
Mが2上がると、Lやu は10倍になる(1上がると√10 = 約3倍になる)
概略的な関係(地震の規模による断層運動のスケーリング)
M 4 5 6 7 8
L (km) 1.3 4 13 40 130
u(m) 0.06 0.2 0.6 2 6
スケーリングの物理的な意味
地震を起こす歪(u/L)はほぼ一定;岩石の強度で決まる
地震の規模は、歪を開放する場所の大きさに対応する
本震・余震型地震と群発地震(図:地震のヒストグラム)
本震・余震型地震
余震は、本震の発生に誘発される地震
あるマグニチュード以上の余震の数は、経過時間にほぼ反比例して減少
例:兵庫県南部地震(1995年)
群発地震
本震に対応する大きな地震が存在せず、類似の大きさの地震が繰り返す
火山地域で起こることが多く、地下水などが関与する場合も
例:神津島沖の群発地震(2000年、最大M6.4)、松代地震(1965-1971年、最大M5.4)
中間的な場合もある;大きな余震、異常に長い余震活動の継続
例:新潟中越地震(2004年)