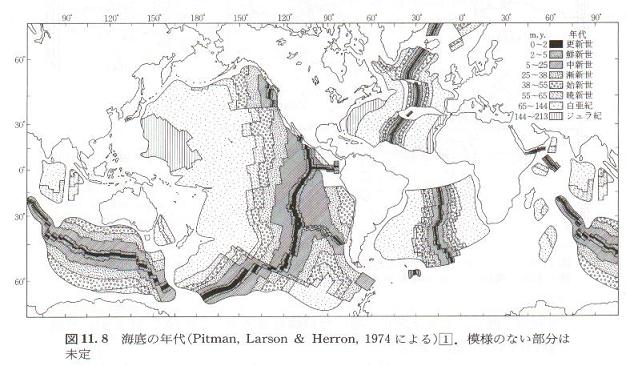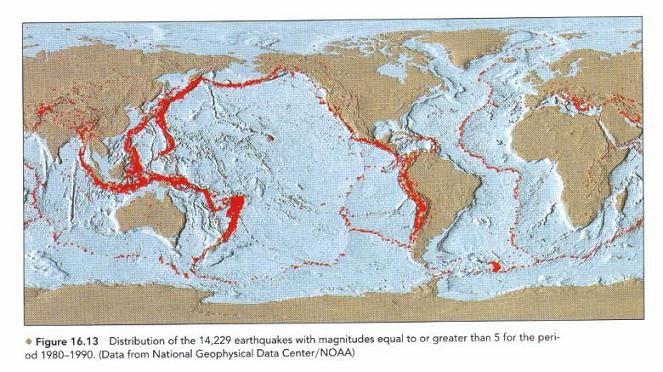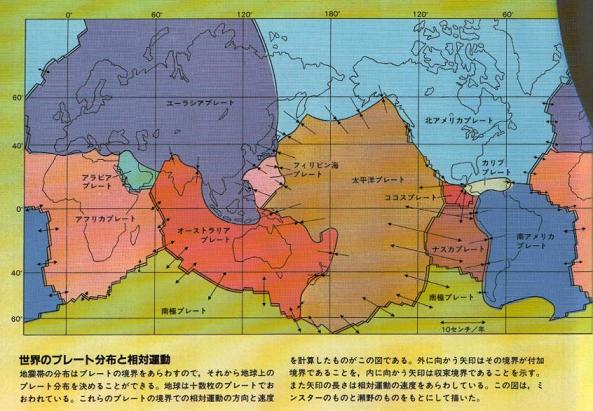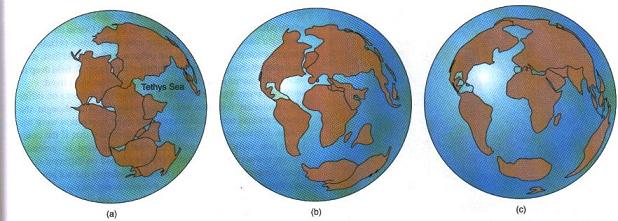3.地球内部の構造と運動
c. 地球内部の運動
外核の対流と地球磁場
地球磁場
地球磁場は、地球の中心に大きな磁石を置いた場合と類似
北に向いてS極、南に向いてN極
磁極は自転軸にほぼ沿うが、自転軸とは完全には一致しない
現在も10°以上ずれていて、数百年の周期で変動する
磁石が作る磁場(双極子磁場)で説明できない部分もある
磁場のNS方向は反転を繰り返してきた
古い岩石の帯磁方向から分かる
逆転の時間間隔はかなり不規則
最も新しい逆転は約80万年前、最近500万年間は平均約20万年毎に逆転
地球磁場の原因
地球内部の高温の状態では、磁石は存在できない
外核はFeを主成分とする液体金属;電流を流す導体の液体
液体の流れ易さは水と同じ程度
外核に存在する導体の流れが、地球磁場の原因
磁場を作るメカニズム:ダイナモ理論
外核に熱対流、対流は自転によるコリオリ力の影響を受ける
導体が動くと、誘導電流が生じ、磁場が発生する
磁場、電流、対流は、相互に作用し合って、自励的に保持される
磁場の反転は、何らかのきっかけで、流れの方向が逆になるため
惑星や衛星に磁場があれば、それは液体の核の存在を示すものと理解
Q. 磁石は、温度を何度くらいまで上げると、磁化を失うか?
マントルの流動
固体の変形や流動
固体は通常の条件で弾性変形をする
力(応力)を加えると変形(歪)が生じ、除くと解消される
弾性波(縦波と横波)が伝播する
力(応力)を強く加えると、破壊する
固体も流動して永久変形することがある;金属の板、蝋
実験室での岩石の変形実験
温度が高くなり、融点にかなり近づくと、流動が検出できる
流動性(粘性率)は、強い温度依存性をもつ
マントルは高温なので、力が加わるとゆっくりと流動する
固体地球で観測される流動(図:後氷期のローレンタイドの隆起)
山脈の褶曲;水平に堆積した地層が、強く曲げられる
氷床後退後の地面のゆっくりとした隆起
約1万年前に氷の荷重が取り除かれ、地殻が流動しながら変形を解消
流動の速度は極めて遅い;数cm/年の程度
[参考]流動性は粘性率(粘度)で表現
粘性率(= 応力/歪速度)は、流動のしにくさを表す
粘性率の目安
マントル:1020 Pa.s 外核:10-3 Pa.s
玄武岩質マグマ:103 Pa.s 流紋岩質マグマ:1011 Pa.s
水:10-3 Pa.s 空気:10-5 Pa.s
Q. マントルは地震波を伝え、なおかつ流動もする。
弾性と流動がどのような条件で起こるか考えよ。
海底地形(図:世界の地形)
海底は、全体としてはかなり平坦な面
平均的な深さは5km程度。島や海山などの起伏もある
海嶺、海溝など、海底全体にわたる大きな構造が見られる
海嶺
相対的に浅い部分;深さは約2.5〜3km
海底を横切って、峰状にどこまでも続く;長さは数千kmかそれ以上
海嶺から離れるにつれて、海底は徐々に深くなる
深さの分布は、海嶺の両側でほぼ対称
海溝
太平洋を囲んで、大陸の淵に深い溝
インド洋、地中海などにも存在
大西洋には、一部を除いて存在しない
深さは場所による;最深部で11km
Q. 日本付近の海底地形には、どんな特徴があるか?
海底の形成年代(図:海底の年代)
海底の年代
海底から火山岩を採取
放射性元素を使って、火山岩ができた年代を測定
海底の年代の分布に顕著な特徴
海嶺付近の火山岩は若い。できたばかり
海嶺から離れるにつれて、火山岩の年代は古くなる
年代分布は、海嶺の両側でほぼ対称
海溝付近の火山岩は極めて古い
海底の年代分布は、1960年頃に地磁気の観測から最初に決められた
岩石は、形成時にその時の地球磁場の方向を反映して磁化する
地球磁場の反転に対応して、磁化方向が変化し、海底に縞模様
Q. 海底の磁化は、どのような方法で測定するか?
[参考]放射年代測定法
放射性崩壊が一定の割合で進行することを利用
マグマから岩石ができるときに、同位体比が固定
その後、放射性元素の崩壊が起きて、同位体比が変化
質量分析計でその量を測と、マグマができた年代が分かる
カリウム・アルゴン法の例: 40K → 40Ar 半減期:1.25×109 年
岩石ができるとき、Arなどのガス成分はマグマから抜ける
その後、ガス成分は固結した岩石中に保持
40Arの現在量から、岩石がどのくらい前にできたかが分かる
実際には、同位体比40Ar/36Arで決める
(40Kは質量数が40のカリウム。圧倒的に量が多いのは39K)
下図:杉村・中村・井田編「図説地球科学」(岩波書店)より
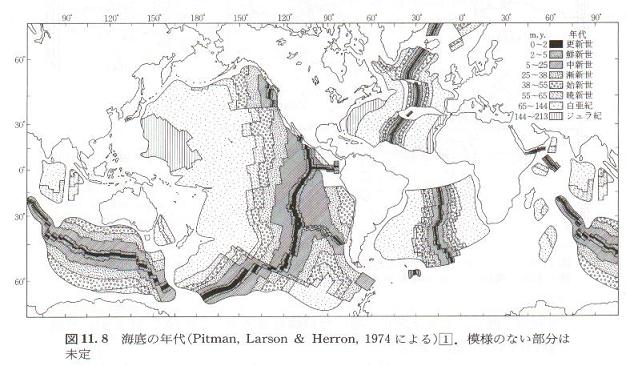
海底の拡大(図:海嶺、トランスフォーム断層、海溝)
海底拡大説
海嶺では、火山の活動によって、新しい海底がマグマから造られる
それ以前に作られた海底は、両側に移動し、海底は拡大する
この過程が繰り返されて、海底ができる
海底の年代は、海嶺からの距離とともに古くなる
海嶺からの距離と年代の関係から、海底が移動する速度が求まる
移動速度は、数〜十数cm/年
大陸に出会わずに海溝まで続く海底では、移動速度は10cm/年程度
海溝に出会わずに大陸に達する海底では、移動速度は数cm/年
地球の表面積は一定に保つ必要
海嶺で作られた面積の分だけ、海底は海溝で消失すると理解
海嶺は一続きではなく、細かく分断されている
海嶺を分断する部分では、拡大を埋め合わせる横ずれが起きている
これをトランスフォーム断層とよぶ
Q. トランスフォーム断層の地形は、段差のついた崖になる。何故か?
地震と火山の分布
地震の震源は、大部分が世界の特定な場所に集中(図:世界の地震の分布)
海嶺とトランスフォーム断層に沿って、ほぼ線状に分布
海溝の陸側には、震源は帯状に集まる
火山も、世界の特定な場所に集中(図:世界の火山の分布)
海溝の陸側に、ほぼ線状に分布
海嶺に沿う海底火山で、新しい海底が形成される
潜水艇で、海嶺軸に溶岩や熱水が観察される(図:海嶺)
熱水のまわりには、陸上とは異なる生物群が生息する
震源や火山は海嶺と海溝付近に集中し、トランスフォーム断層に地震
これらの場所には歪やマグマが局在し、地震や噴火が起こる
それ以外の場所は、地震や火山の活動が低調
下図:E.J.Tarbuck & F.K.Lutgens "Earth"(Prentice Hall)より
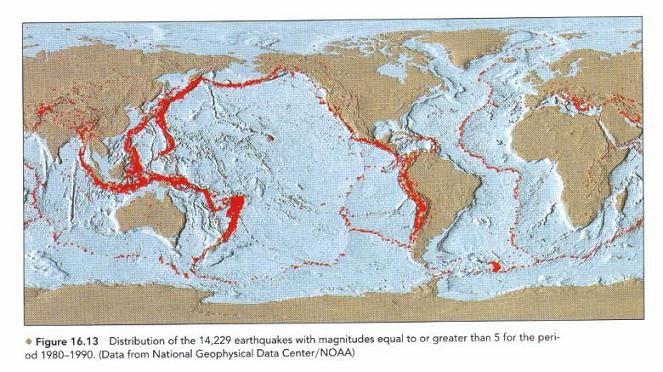
Q. 海嶺の生物は、生存のためのエネルギーをどこから得ているか?
プレート
海嶺、海溝、トランスフォーム断層には、変動が集中
それ以外の場所は、変動をほとんど受けない
この変動の少ない部分をプレートと呼ぶ
プレートは、海嶺で作られて海底を移動する
海溝で沈み込むものもある
大陸を乗せて移動するものもある
プレート同士は、海嶺、海溝、トランスフォーム断層で接する
海嶺、海溝、トランスフォーム断層は、プレートの境界
海溝付近の地震(図:日本列島付近の震源分布)
震源の分布は非対称で、海溝の陸側に偏っている
地下に沈み込んだプレートの延長上に、深発地震が発生
海側のプレートは海溝で地下に沈みこむが、陸側は沈み込まない
海洋地殻は沈みこむが、大陸地殻は沈み込まない
大陸地殻と海洋地殻は性格が異なる
Q. 海嶺、海溝、トランスフォーム断層を境に、プレートはどう動くか?
大陸地殻と海洋地殻
大陸地殻と海洋地殻は、厚さや形成年代が全く異なる
両方ともマグマから造られるが、形成環境が異なる
海洋地殻は、海嶺で形成され、海溝で地球内部に戻る
大陸地殻は、一度形成されると、地球表面に留まる
初期に中核部(クラトン)が造られた後、まわりに徐々に成長
大陸と海洋の差は、地殻より下のマントルにも及ぶ
海洋地殻 大陸地殻
厚さ 5〜8 km 20〜70 km
形成年代 2億年前〜現在 38億年前〜現在
化学組成 マフィック マフィック〜フェルシック
構造 上 堆積岩 堆積岩、各種火山岩
玄武岩 カコウ岩
下 ガブロ ガブロ
Q. 大陸地殻が沈み込まない理由を考察せよ
プレート・テクトニクス
プレート・テクトニクス:各種の事実を整理し、体系化したもの
地球の表面は、複数のプレートでできている
プレートは、ほとんど変形せずに地表を移動する;剛体で近似
地震や火山の活動は、主にプレートの境界で起こる
プレートの境界は、海嶺、海溝、トランスフォーム断層のどれか
海嶺:新しいプレートが造られ、両側に広がる場所(発散境界、付加境界)
海溝:海底を乗せた海洋プレートが地球内部に沈み込む場所(収束境界)
トランスフォーム断層:2つのプレートが水平にすれ違う場所
プレート運動の特徴
海嶺の活動は対称、両側に新しいプレートを造り、拡大させる
海溝の活動は非対称、海側のプレートだけが地球内部に沈み込む
大陸は、沈み込まずに、地表に存在し続ける
Q. プレートの運動速度を測定する方法を列挙せよ?
プレートの分布(図:世界のプレートの分布、日本付近のプレートの分布)
地震の分布を参照して、プレートの分布を描く
海嶺は、トランスフォーム断層で切られながら、太平洋、大西洋、インド洋などを縦断
海溝は、主に太平洋のまわりに分布
世界には、7大プレートと多数の小プレート
7大プレート
太平洋、ユーラシア、北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、
オーストラリア、南極
日本付近のプレート:北アメリカ、ユーラシア、太平洋、フィリピン海
太平洋プレートが北アメリカ、フィリピン海の両プレートの下に沈みこむ
ユーラシア・プレートは、北アメリカ・プレートの下に沈みこむ傾向
下図:竹内均監修「生きている地球」(教育社)より
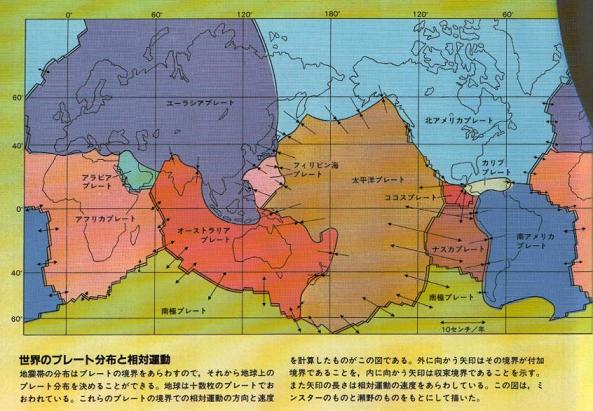
Q. 太平洋プレートは、どのようなプレート境界に囲まれているか?
大陸の分裂と移動(図:大陸の分裂と移動の歴史)
大陸移動説:昔は大陸が一体だったという考え
大西洋をはさんで、海岸線の形が類似、化石などに連続性
昔存在した唯一の超大陸パンゲアが、その後分裂して移動した
ウェゲナーが1912年に提案
大陸移動説は一時すたれた;運動の原動力などの問題
20世紀半ばに、海底拡大説やプレート・テクトニクスと融合して復活
大陸は分裂して、間に海嶺ができる
海嶺での海底の拡大につれて、大陸は離れていく
大陸移動の詳細
1.8億年前頃:大西洋中部の拡大開始、パンゲアの中部が南北に分離
インド洋の拡大で南極大陸とインドが分裂
1億年前頃:アフリカと南米が分裂
0.6億年前頃:ユーラシアと北米が分裂、インドがユーラシアに衝突
下図:E.W.Spencer "Earth Science"(Mc Graw Hill)より
(a)1.8億年前 (b)0.8億年前 (c)0.3億年前
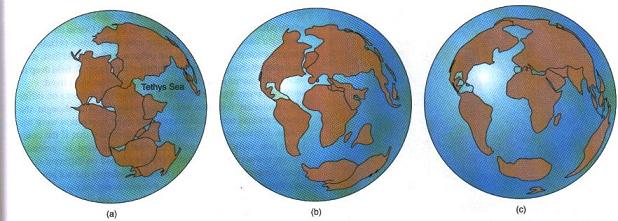
Q. プレートに運ばれた大陸が、他の大陸に衝突したら何が起こるか
ホットスポット(図:ホットスポット火山の分布)
ホットスポット火山:プレート境界から離れて、孤立して活動
例:ハワイ、レユニオン、イエローストーン
現在活動的な火山は、火山列の終端
そこから離れるにつれて、火山の年代は古くなる
ホットスポット仮説
マントル上部には、高温のホットスポットがあり、地表にマグマを供給
ホットスポットの真上で、火山(ホットスポット火山)が形成
古い火山は、プレートの運動によって次々に運び去られ、火山列ができる
世界中には、数十個のホットスポットがある
ホットスポットの位置は、プレート運動とほぼ無関係に、相互に固定
ホットスポットは、マントル深部に根をもつ
Q. ハワイから始まる火山列は、途中で何故折れ曲がるか?
プレート・テクトニクスとマントル対流(図:マントル対流)
地震波速度のトモグラフィー
マントルの地震波速度の分布が、3次元的に調べられている
高速度は低温、低速度は高温を意味するとして、水平方向の温度分布が推定
海洋プレートの下に低速度層
プレートを動かす潤滑層アセノスフェアが存在
低速度層の始まる深さから、海洋プレートの厚さは数十〜100km
大陸の下では、低速度は余り顕著でなく、深さも深い
大陸を乗せたプレートの運動速度が遅い理由
プレート・テクトニクスとマントル対流の関係
海嶺の下には低速度層が発達しているが、マントルの上部に局在
海溝で沈み込むプレートに対応して、その下に高速度の部分
場所によってはマントルの底まで追跡
ホットスポットが多く分布する地域は、マントル深部が低速度になる傾向
マントル対流の様式
プレートの沈み込みに対応して、マントルの下降流がマントル深部まで
マントルの上昇流は、ホットスポットの活動と対応しそう
海嶺は、深部に根をもたず、プレートが引き裂かれた部分と理解
関連する問題
Q1. 海嶺から離れるにつれて、海底が深くなるのは何故か?
Q2. 海嶺と海嶺の間には、何故トランスフォーム断層ができるか?