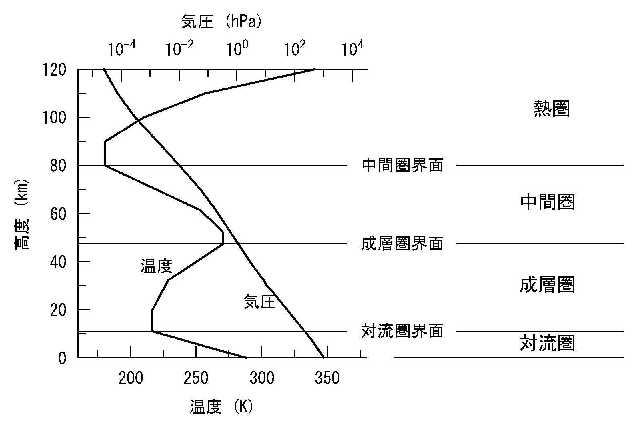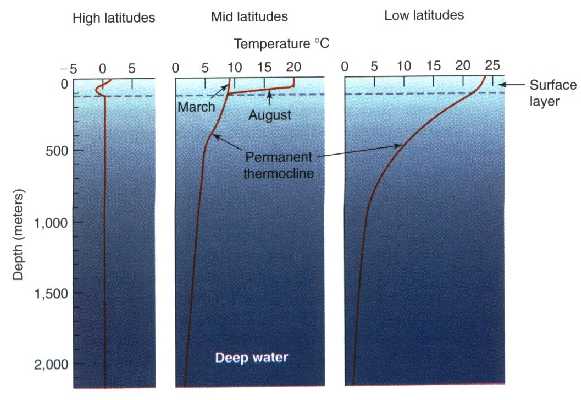2.地球環境
a. 大気と海の状態
大気の状態(図:大気の温度と圧力)
地表付近の温度(気温)と圧力の変化
地表 温度 15 ℃ 圧力 1 気圧
1 km 上空 8 ℃ 0.8気圧
3 km 上空 -4 ℃ 0.7気圧
10 km 上空 -50 ℃ 0.3気圧
温度は6.5℃/kmの割合で下がる
圧力は5km上昇する毎に半分になる
大気全体を通じて高さの関数として見る
圧力は、高さとともに単調に、指数関数的に減少
高さが数倍高くなると、圧力は数桁小さくなる(圧力の目盛は対数)
温度は、下降と上昇を繰り返す
温度と圧力の単位
温度;絶対温度Kは摂氏に273℃を加えたもの(-273℃が0 K)
圧力:1気圧=1,013 hPa (hPa=100 Pa)
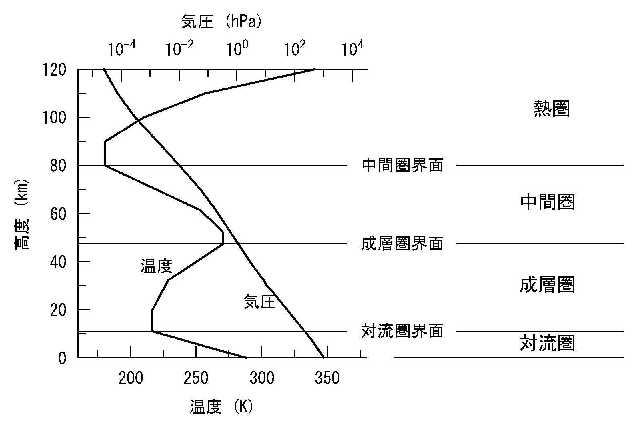
Q. 高山病はどのような原因で発生するか?
圧力の分布
大気の圧力は、高さとともに指数関数的に減少
圧力と密度の間の相乗効果による
圧力は、その高さより上にある荷重の合計できまる
大気の密度が一定ならば、圧力は高さとともに直線的に減るはず
現実には、密度は圧力に比例して変化する(ボイルの法則)
圧力と密度は、お互いに関係しあって、高さとともに著しく減少
地表:圧力1気圧、大気の密度1.23 kg/m3
[参考]
圧力pは高さhより上の荷重で決まる dp/dh = -gρ
g 重力加速度、ρ大気の密度
ρはpに比例(ボイルの法則) p = (RT/M)ρ
R ガス定数、M 大気の平均分子量、T 絶対温度
dp/dh = -(gM/RT)p から p, ρ ∝ exp(-(gM/RT)h)
温度などはほぼ一定と仮定
Q. 高さ5kmの山の上では、酸素は地表よりどの程度減少するか?
温度の分布
温度の分布は極大と極小をもつ
極大と極小を境に、大気を下から対流圏、成層圏、中間圏、熱圏に分ける
その境界(圏界面)は、緯度などに依存し、時間的にも変化する
温度は、大気に出入りするエネルギーの収支で決まる
基本的なエネルギーは、太陽から入射する電磁波で、その大半は地表で吸収
温度は地表が高く、上空にいくほど下がる傾向
地表付近は、温度の時間変化が大きく、逆転層も生じうる
温度分布が極大と極小をもつのは、途中でエネルギーの吸収があるため
高さ10〜40kmでオゾンO3層が紫外線を吸収し、成層圏で温度が上昇
高さ80km以上では、OやNが短紫外線やX線を吸収し、熱圏で温度が上昇
このような温度分布は、酸素の多い地球特有のもの
Q. 熱圏や成層圏の温度上昇には、多量の熱はいらない。何故か?
大気の区分(図:地球をとりまく大気)
対流圏:地表〜高度約10km
地表で加熱されるために、大気は不安定で、複雑な対流が発生
水蒸気は、上昇とともに凝結し、雲になって、雨や雪として降る
地表付近の気象条件は、対流圏の状態に支配される
成層圏:高度約10km〜高度約50km
温度勾配が逆転するために、対流圏での大気の運動を押さえる効果
雲は存在しないが、下部に偏西風、ジェット気流などの強い流れ
ジェット機の通行などに利用される
中間圏:高度約50km〜高度約80km
大気の状態は対流圏ほど不安定でない
最上部では雲ができる。極地方の夜光雲
中間圏から熱圏にかけて、極地方ではオーロラが発生
熱圏:高度約80km〜高度約300km
空気が希薄で、一部がイオン化し、プラズマ状態になっている
電離層は、地表からの電波を反射して、情報の伝達に寄与
熱圏は上部で磁気圏につながる
Q. 成層圏で雲ができないのは何故か?
海の温度と圧力(図:海の温度)
海水の温度は、海面付近が一番高く、深部で一定値に近づく
太陽の熱が主に地表付近で吸収されるため
1kmよりも浅い部分では、温度は緯度に依存し、季節によっても変わる
それより深い部分では、温度は場所や深さによらず、ほぼ一定値;1〜2℃
海水の密度は、深さとともに1.024 g/cm3から1.028g/cm3まで増加
密度の変化は、圧力、温度、塩分の量を反映
塩分の量は、場所や深さによるが、約3.5%
圧力は、深さとともにほぼ一定の割合(0.1気圧/m)で増加
下図:E. W. Spencer "Earth Science:Understanding Environmental Systems"
(Mc Graw Hill)より
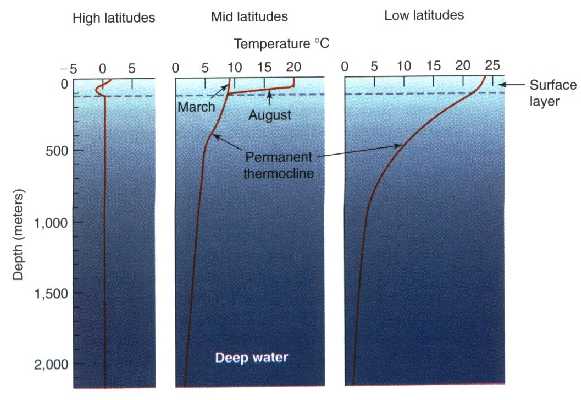
Q. 海の圧力が深さとともにほぼ一定の割合で増加するのは何故か?